A3サイズ縦書き賞状の見本~賞状・表彰状・感謝状・認定証
筆耕コムに掲載している賞状の見本はできるだけ更新するようにしています。今回は更新用に書いた5枚の賞状(賞状・表彰状・感謝状・認定証)をご紹介します。
手書きの賞状なので、どうしてもその時々によって文字の雰囲気が変わります。この変化は微妙なのですが、書いている僕自身としては大きな違いに感じます。
納品された賞状が「HPの見本と違う」と思われたくはありません。今現在の僕の書く文字をできるだけ伝えたいので、1年に1度の更新はとても重要な作業になっています。本当に微妙な違いなんですけどね。
サイズは標準のA3サイズ。文字の向きは縦書き(用紙横向き)。全文手書きの賞状です。※専門用語が多々出てきますがお許しください。
賞状見本①『表彰状』受者1行・主文6行・贈者1行

受者名1行、贈者名も1行のオーソドックスな表彰状です。文字の大きさがは『表題>受者名>贈者名>主文>日付』
徳井さんの『徳』に横棒が1本余計に入っていますが、これは旧字体です。お名前では旧字の徳をよく見かけます。
賞状見本②『感謝状』受者1行・主文6行・贈者1行

この感謝状も実にオーソドックスなパターンです。。
賞状の主文は2文で書かれることがほとんどです。前半が受者の実績や功績、後半が表彰や感謝の言葉です。
主文の改行は1か所が原則です。3つの文章であっても改行は1か所にします。『よって~』がある場合はその前で改行し、『よって~』が必ず文頭に来ます。
賞状見本③『認定証』受者3行・主文5行・贈者2行

この『認定証』は賞状の中では複雑な部類に入ります。特に、受者部分が3行あるので、文字の大きさや書き出し位置に注意が必要です。
また、最も右に『証書番号』が入るので、レイアウト全体に大きな影響を与えることになります。
卒業証書も右端か左端に『証書番号』が入るので、実はとてもレイアウトが難しいのです。
そんな難しい卒業証書はぜひ筆耕コムにご依頼ください。版下大歓迎です。※版下…印刷のもと
賞状見本④『賞状』受者2行・主文4行・贈者1行

賞状全体の行数が9行と少ない、シンプルな賞状です。・・・が、『優秀賞』が入ることで難易度がグッと上がります。
『優秀賞』は文字の大きさと書き出し位置に注意が必要で、賞状全体のバランスに大きな影響を与えてきます。
賞状見本⑤『賞状』受者2行・主文4行・贈者1行

賞状見本④の『賞状』と全く同じ行数ですね。※しまった!かぶった。
④と⑤が被っているのは、このブログを書いているときに気が付きました。これでは芸が無いですね。
レイアウトは④と同じです。やはり『優秀賞』の書き出し位置と文字の大きさがポイントになります。
まとめ
今回5枚の賞状をご紹介して気が付いたかもしれませんが、賞状は文字を書く技術と同様にレイアウトの技術が重要です。
どちらの方が重要か?と比べることはできませんが、書く為の技術は書写(国語)、レイアウトは算数(数学)の要素が強いので、両方ともしっかりと習得する必要があります。
今回は5種類の見本を掲載しました。賞状の種類は無限にあるので、また少し書いたらご紹介していこうと思います。
複雑になればなるほど、賞状は面白いのです♪




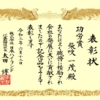




ディスカッション
コメント一覧
初めまして。
埼玉県さいたま市に在住の飯田真澄と申します。
20年ほど前に、一度筆耕(賞状書士)の仕事に就きたいと思い、育児の傍ら独学で勉強し始めたものの、なかなか時間が取れず、中途半端に終わってしまいました。
子ども達が成人した今、賞状を書いたり、筆耕の仕事をしたいと思うようになりました。
ちなみに今、学童クラブの児童指導員として週5日の勤務に就いています。
書道歴は長く、息子が小学生の時にスポーツ少年団(サッカー)に入ってた頃、クラブ内での試合で使う賞状の筆耕を頼まれ、書くこともありました。
仕事となると、民間資格等を取得して、それからになるのでしょうか。
副業的に賞状書士の仕事ができればと考えていますが、それまでにはかなりの年月もかかるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、お話を聞かせていただければと思い、思いきってメールをさせてもらいました。
お時間のある時で構いませんので、どうぞよろしくお願い致します。
飯田真澄
飯田さん
こんにちは、清水です。
コメントありがとうございます。
筆耕のお仕事ですが、民間資格は必要ありません。自分に技術と知識があれば、今すぐにでも始めても良いと思います。
ただ、賞状を書く場合は専門の技術と知識が少なくないので、独学だと難しいでしょう。
まずは、筆耕の仕事にはどのような種類があるのか?どの程度の技術が必要なのか?などを筆耕業者のホームページ等で調べてみると良いかもしれません。
また、年月がかかるかどうかは本人次第だと思います。10年経っても上達しない人もいれば、1年で信じられないほど上達する人もいます。
目標をもって、楽しみながら練習できれば最高ですね。
以上、参考になれば幸いです。
清水克信
下記サイトも参考にしてみてください。
https://筆耕の仕事.com/